さまざまな国籍や宗教、世代や価値観、障害やライフスタイルがある人が、同じ街や地域、職場や学校で交わるようになり、それぞれのちがいに戸惑う機会も増えてきました。
私たちはすべての人に共通する食という切り口から、ちがいをバリアではなくバリューに変えて、誰もが自分らしく多様性あふれる共生社会をつくります。
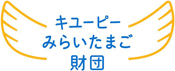
| 財団について |  |
事業内容 |  |
助成団体活動紹介 |  |
助成募集について |  |
財団ブログ |  |
子ども向けサイト |
2021年度 食育活動
特定非営利活動法人インターナショクナル

誰もが自分らしく多様性あふれる未来へ |
特定非営利活動法人インターナショクナル
代表者:菊池 信孝
所在地:兵庫県神戸市灘区水道筋3−4
所在地:兵庫県神戸市灘区水道筋3−4
設立年月日:2009年10月5日
連絡先:hello@designtodiversity.com
連絡先:hello@designtodiversity.com
助成申請事業名:小中学校への「食育×多文化」授業提供と児童生徒・教員・提供者の効果測定とwithコロナの学びの拡大と深化に向けたオンライン学習コンテンツの提供
助成金額:85万円
助成事業概要: [概要]
現在、キユーピーみらいたまご財団のご支援と兵庫県栄養教諭協会・神戸市教育委員会の協力のもと、食を起点に多文化や多様性について学べる出前授業「ワールド食育」を関西の小中学校に提供しています。コロナ収束が見えないなか、出前授業の継続・発展を図るとともに、オンラインで学びを支援する動画コンテンツを提供します。
[事業の目的]
①出前授業の継続・発展による多文化や多様性への理解促進と、児童生徒・教員・ファシリテーターの効果測定
ワールド食育は2018年に神戸市教育委員会の「多文化理解モデル授業」認定を経て、2019・20年度は貴財団の支援を賜り27回2,680名に提供。また20年度には新規3名のファシリテーターが参画し(計7名)、複数のクラスに同時に提供し三密を回避できる体制が整いました。21年はこの取り組みを継続・発展させるとともに、社会的インパクト評価の手法を用い、児童生徒・教員・ファシリテーターに生じる意識や行動の変容を測定・可視化します。
②食に不自由を抱える多様な人々の存在と、課題解決に向けた工夫を紹介する動画コンテンツのオンライン提供
共生社会づくりにおける「言葉・文化・理解」の3つの壁を軸に、多様な外国人や障害者へのインタビューを実施し、それぞれが直面する食の課題とその解決に向けた工夫を動画コンテンツとしてYouTubeに公開。全国の教育機関が授業で利用できたり、興味のある児童生徒が個別に見られるように提供し、学びの機会拡大と深化を促します。
[事業の内容]
①については、従来の企業人材によるプロボノ参画に加えて、20年度は新たに出前授業提供先の学校教員や国際交流協会の職員からも参画希望の声をいただきました。多様なファシリテーターの参画促進と授業品質の維持向上を両立させながら、提供できる件数と体制を拡充できるように取り組みます。また出前授業時に児童生徒が記入するリフレクションシートによる評価に加え、学校教員やファシリテーターにもどのような意識や行動の変化が生じているかを社会的インパクト評価の手法を用いて測定し、本事業の成果を可視化します。
②については、例年10月以降に①の開催希望が集中するため、それまでの期間に普段の食生活に不自由を抱えている多様な外国人や障害者へのインタビューを実施し、当事者の言葉と体験を通して課題の提示と解決に向けた工夫を伝えます。またその内容は学習コンテンツとしてYouTubeで公開し、誰もが利用できるように提供します。
助成金額:85万円
助成事業概要: [概要]
現在、キユーピーみらいたまご財団のご支援と兵庫県栄養教諭協会・神戸市教育委員会の協力のもと、食を起点に多文化や多様性について学べる出前授業「ワールド食育」を関西の小中学校に提供しています。コロナ収束が見えないなか、出前授業の継続・発展を図るとともに、オンラインで学びを支援する動画コンテンツを提供します。
[事業の目的]
①出前授業の継続・発展による多文化や多様性への理解促進と、児童生徒・教員・ファシリテーターの効果測定
ワールド食育は2018年に神戸市教育委員会の「多文化理解モデル授業」認定を経て、2019・20年度は貴財団の支援を賜り27回2,680名に提供。また20年度には新規3名のファシリテーターが参画し(計7名)、複数のクラスに同時に提供し三密を回避できる体制が整いました。21年はこの取り組みを継続・発展させるとともに、社会的インパクト評価の手法を用い、児童生徒・教員・ファシリテーターに生じる意識や行動の変容を測定・可視化します。
②食に不自由を抱える多様な人々の存在と、課題解決に向けた工夫を紹介する動画コンテンツのオンライン提供
共生社会づくりにおける「言葉・文化・理解」の3つの壁を軸に、多様な外国人や障害者へのインタビューを実施し、それぞれが直面する食の課題とその解決に向けた工夫を動画コンテンツとしてYouTubeに公開。全国の教育機関が授業で利用できたり、興味のある児童生徒が個別に見られるように提供し、学びの機会拡大と深化を促します。
[事業の内容]
①については、従来の企業人材によるプロボノ参画に加えて、20年度は新たに出前授業提供先の学校教員や国際交流協会の職員からも参画希望の声をいただきました。多様なファシリテーターの参画促進と授業品質の維持向上を両立させながら、提供できる件数と体制を拡充できるように取り組みます。また出前授業時に児童生徒が記入するリフレクションシートによる評価に加え、学校教員やファシリテーターにもどのような意識や行動の変化が生じているかを社会的インパクト評価の手法を用いて測定し、本事業の成果を可視化します。
②については、例年10月以降に①の開催希望が集中するため、それまでの期間に普段の食生活に不自由を抱えている多様な外国人や障害者へのインタビューを実施し、当事者の言葉と体験を通して課題の提示と解決に向けた工夫を伝えます。またその内容は学習コンテンツとしてYouTubeで公開し、誰もが利用できるように提供します。
最新情報はこちら
▲ ページトップへ
| プライバシーポリシー | © Kewpie Mirai Tamago Foundation |