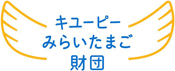
| 財団について |  |
事業内容 |  |
助成団体活動紹介 |  |
助成募集について |  |
財団ブログ |  |
子ども向けサイト |
2019年度 食を通した居場所づくり支援
NPO法人 地域こども包括支援センター

地域とこども達を繋ぎ、ワクワクを発信します。 |
NPO法人地域こども包括支援センターは、地域の子ども達への福祉活動を通して、経済的貧困家庭の児童・生徒に対し食事の提供、学習支援、居場所づくり、伝統文化の継承やリユース・リサイクルの啓蒙活動などから地域との連携を築き、子ども達の健全な成長と社会育成に寄与することを目的に活動しています。
NPO法人 地域こども包括支援センター
代表者:野口峻平
所在地:埼玉県越谷市越ケ谷2丁目9-6
所在地:埼玉県越谷市越ケ谷2丁目9-6
設立年月日:2017年2月22日
連絡先:048-964-8000
連絡先:048-964-8000
助成申請事業名:間久地区 多世代交流居場所づくり事業
助成金額:50万円
助成事業概要: 助成事業の内容
県営住宅をプラットホームとした「多世代交流施設」の運営
県営住宅及び近隣住民を対象とした非認知能力(体験を主とする)学習支援及びこども食堂による食育支援。これまで既存の施設において実施した非認知能力を育む学習支援※1と、新たに保健所の基準で不特定多数の参加が可能な食堂施設を兼ね備えます。
高齢者と子ども達、学生が参加し、それぞれがアシスタント兼参加者となることで、地域との繋がりや自己肯定感を得て負の連鎖を断ち切る地域コミュニティーの再構築を目指します。学習支援の流れで食事の提供を行います。
・地域自治会・近隣小学校とも連携し参加者への周知を行い、週3回朝ごはんの提供、昼ごはん(学校長期休業時)、夕ごはんの提供を行います。孤食の高齢者を調理員などの担い手とし、共に食事もして頂きます。
・食品は、これまでと同様にフードバンク、独自のフードドライブ事業※2から供給します。
・ボランティアもこれまでと同様、近隣大学生、市民活動団体、近隣高齢者との協働とします。
・場所は埼玉県の無償提供。これにより、運営上の障害である食品の確保・人(ボランティア)の確保・場所の確保について運営費がほぼかからず、持続が可能となります。
・新たに、主に高齢者と、冬季(日暮れの早い時期)の夜間に帰宅する子ども達を対象とした送迎を行います。これにより住む場所によって参加の可否となる格差を解消し、他地域への同様施設の開設啓蒙に繋げます。
※1 お金の勉強(東京スター銀行協働)、防災の勉強(県の防災士)、伝統文化継承(落語・左官技術の光る泥団子作り)、パン・ケーキ・ピザを焼こう(地域各専門家)、手品を学ぼう(地域愛好家)、パステルアートを学ぼう(地域専門家)、セラバンド健康体操(地域インストラクター)、美文字を書こう(地域書道家)など。すべてボランティア講師。
※2 埼玉県「彩の国こども応援ネットワーク事業」から派生した民間企業連携の食品確保
助成金の執行計画
2019年2月 必要調理器具、施設内設置家電、
食事時に使用する折畳式机(10脚を予定)椅子(30脚を予定)購入予定
2019年2月末 活動開始
2020年3月 活動報告パンフレットの発行
その他 多世代交流事業イベント(年4回開催予定)開催 スタッフ各種研修実施 他県視察などを予定
助成の成果の公表方法
経済的な貧困にかかわらず、地域との孤立を心の貧困ととらえ、児童と高齢者との関わりからそれぞれが自己肯定感を得ることが出来るようになる。参加者アンケートから実施前、実施後の実感を数値化し公表する。
助成金額:50万円
助成事業概要: 助成事業の内容
県営住宅をプラットホームとした「多世代交流施設」の運営
県営住宅及び近隣住民を対象とした非認知能力(体験を主とする)学習支援及びこども食堂による食育支援。これまで既存の施設において実施した非認知能力を育む学習支援※1と、新たに保健所の基準で不特定多数の参加が可能な食堂施設を兼ね備えます。
高齢者と子ども達、学生が参加し、それぞれがアシスタント兼参加者となることで、地域との繋がりや自己肯定感を得て負の連鎖を断ち切る地域コミュニティーの再構築を目指します。学習支援の流れで食事の提供を行います。
・地域自治会・近隣小学校とも連携し参加者への周知を行い、週3回朝ごはんの提供、昼ごはん(学校長期休業時)、夕ごはんの提供を行います。孤食の高齢者を調理員などの担い手とし、共に食事もして頂きます。
・食品は、これまでと同様にフードバンク、独自のフードドライブ事業※2から供給します。
・ボランティアもこれまでと同様、近隣大学生、市民活動団体、近隣高齢者との協働とします。
・場所は埼玉県の無償提供。これにより、運営上の障害である食品の確保・人(ボランティア)の確保・場所の確保について運営費がほぼかからず、持続が可能となります。
・新たに、主に高齢者と、冬季(日暮れの早い時期)の夜間に帰宅する子ども達を対象とした送迎を行います。これにより住む場所によって参加の可否となる格差を解消し、他地域への同様施設の開設啓蒙に繋げます。
※1 お金の勉強(東京スター銀行協働)、防災の勉強(県の防災士)、伝統文化継承(落語・左官技術の光る泥団子作り)、パン・ケーキ・ピザを焼こう(地域各専門家)、手品を学ぼう(地域愛好家)、パステルアートを学ぼう(地域専門家)、セラバンド健康体操(地域インストラクター)、美文字を書こう(地域書道家)など。すべてボランティア講師。
※2 埼玉県「彩の国こども応援ネットワーク事業」から派生した民間企業連携の食品確保
助成金の執行計画
2019年2月 必要調理器具、施設内設置家電、
食事時に使用する折畳式机(10脚を予定)椅子(30脚を予定)購入予定
2019年2月末 活動開始
2020年3月 活動報告パンフレットの発行
その他 多世代交流事業イベント(年4回開催予定)開催 スタッフ各種研修実施 他県視察などを予定
助成の成果の公表方法
経済的な貧困にかかわらず、地域との孤立を心の貧困ととらえ、児童と高齢者との関わりからそれぞれが自己肯定感を得ることが出来るようになる。参加者アンケートから実施前、実施後の実感を数値化し公表する。
最新情報はこちら
▲ ページトップへ
| プライバシーポリシー | © Kewpie Mirai Tamago Foundation |